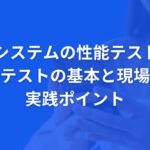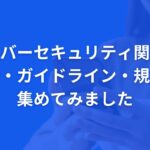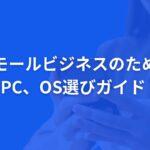システムトラブル報告書、よくある3つの盲点:再発防止につながる報告書の作り方

本記事では、効果的なシステムトラブル報告書の作成方法と、よくある問題点についてご説明します。
システムを運用していると、「トラブル報告書を作成したものの、同様の問題が再発してしまう」「報告書の内容が現場の改善に活かせない」といったことをよく目にします。なぜこのようになってしまうのか、よくある盲点と効果的な報告書の作成方法をご紹介します。
盲点1:事象の記載に終始している
よくある記載例
3月1日 10:30 システム障害発生
3月1日 10:45 ベンダーへ連絡
3月1日 11:30 システム復旧
原因:サーバーの負荷増大
対策:サーバーを再起動問題点
このような報告書では、なぜ負荷が増大したのか不明であり、再起動以外の対策を検討していません。また、予兆があったかどうかも記載されていません。
改善案
より効果的な報告書にするためには、以下の観点を追加しましょう:
- 発生までの経緯(前日からの状況、通常時との違い、警告の有無)
- 影響範囲の詳細(影響を受けた業務、対応に要した工数、関連システムの状況)
- 根本的な原因分析(負荷増大の原因、監視体制の適切さ、システム設計の問題点)
盲点2:対策が場当たり的
よくある対策例
対策:
1. 監視を強化する
2. 手順書を見直す
3. 定期的にメンテナンスを実施する問題点
この例では具体的な実施内容が不明確で、効果の確認方法が未定義であり、責任者も明確になっていません。
改善案
対策は以下の要素を明確にしましょう:
- 具体的な実施事項
- 監視項目の追加(CPU使用率、メモリ使用率など)と適切なアラートのしきい値設定
- 定期メンテナンスの具体的な実施項目
- 実施時期と担当者の明確化
- 例:3月中に監視項目追加(担当:山田)、4月から定期メンテナンス開始(担当:鈴木)
- 効果確認方法
- 監視レポートの定期確認、性能評価の実施、四半期ごとのレビュー
盲点3:ベンダーとの情報共有が不足
よくあるコミュニケーション例
ベンダーに調査を依頼
→ 原因は負荷増大と報告を受ける
→ 再発防止策を検討中問題点
このような対応では、詳細な調査結果が共有されず、類似事例の有無も不明です。また、中長期的な対策も検討されていません。
改善案
ベンダーとの協議では、技術的な詳細(ログ分析結果、設計上の課題、類似事例)、今後の対策(システム改修の必要性、運用方法の見直し)、継続的な改善策(定期的な状況報告、予防保守の提案)について具体的に話し合いましょう。
効果的な報告書作成のポイント
- 目的を明確に 報告書は単なる記録ではなく、経営層への説明資料、再発防止の実行計画、そして組織のナレッジ蓄積としての役割があります。
- 必要な情報を漏れなく 事象の概要、発生原因、影響範囲、対応内容、再発防止策という基本要素を押さえることが大切です。
- 具体的な対策を示す 実施事項、担当者、期限、効果確認方法を明確にして、実行可能な計画にしましょう。
まとめ
トラブル報告書は単なる記録ではなく、再発防止と業務改善のための重要なツールです。形式的な作成に終わらせず、実効性のある内容を心がけましょう。
また、トラブルの予防には、十分な性能テストを行ない、問題点を把握しておくのも効果的です。
性能テストについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
当社では、システムトラブルの原因分析から、効果的な再発防止策の立案までのさまざまな技術支援を提供しています。
システムトラブルでお困りの際は、ぜひご相談ください。


















は必要か-150x150.jpg)